ウンケー?ナカヌヒー?ウークイ?
「なにその呪文」って思ったそこのアナタ。わかる。俺も最初はそうだった。沖縄に来るまで、お盆っていえば『親戚の家でナスとキュウリ飾るイベント』だと思ってたからな。
ところがどっこい。沖縄のお盆は『3日間ぶっ通しのご先祖様ウェルカム祭り』です。
親戚は集まるわ、爆竹は鳴るわ、エイサーは踊るわ。そのテンション、ほぼ年越しレベル。むしろご先祖様のためのカウントダウンイベントか?これ毎年楽しそうなんだけど?俺の地元、線香の匂いしかしなかったぞ。
でもね、騒がしく見えて、その裏には『魂を迎えて送り出す』っていう、超大事な意味と伝統がちゃんと詰まってるんですよ。
この記事では、そんな沖縄独特のお盆文化『ウンケー(お迎え)/ナカヌヒー(中日)/ウークイ(お見送り)』の三日間を、緩く、でもちゃんと、深掘りしてみます。羨ましいから、俺もちょっと混ぜて。
沖縄のお盆とは?
本土と何が違う?
- ないちゃー「お盆って家で静かにナスの牛とキュウリの馬並べて…」
- うちなーんちゅ「それは「ご先祖様これ乗り物でよろしく!」のヤツな。でも沖縄ではそんな静かな儀式は存在しねぇ」
本土のお盆
迎え火、送り火、お墓参り、ナスとキュウリ、あと親戚との気まずい団らん。
沖縄のお盆
ご先祖様が帰省してくる想定で、親戚一同が家をピカピカに掃除し、料理作りまくり、線香に火を灯し、爆竹と太鼓でウェルカムムード全開。あと、エイサーが爆音で地元を練り歩く。夜なのにうるさい。最高。
沖縄独自の3日間『ウンケー/ナカヌヒー/ウークイ』
沖縄では、お盆はこの3日間がセット。名前だけでいえば呪文。意味を知ると、ちゃんと筋が通ってる。
[迎え]ウンケー
お盆の初日。ご先祖様、いらっしゃーい。仏壇に線香を立てたり、玄関に迎え火を焚いてご先祖様を迎える。爆竹が鳴り響くのは『あの世の門を開く合図』という説も。ちなみに沖縄の爆竹、鼓膜が死ぬレベル。音がデカすぎて、迎える前に現世の住人の魂が抜けるわ。
[中日]ナカヌヒー
真ん中の日。宴会とエイサーの日。親戚が集まって飲み会したり、エイサー隊が地域を回って踊りまくる。エイサーの太鼓が夜中に鳴り響くけど、苦情はゼロ。むしろ「来たぁあぁあ!」とテンション上がる地元民。うるさい?それ風情って言うんですよ。
[送り]ウークイ
最終日「じゃあな、ご先祖また来年な」って送り出す日。重箱に『ウサンミ(おかず)』を詰めて『紙銭(ウチカビ)』を燃やして、あの世の生活費を支給する。いや、死んだ後も仕送り必要なの?物価上がってんの?地獄のインフレ深刻なの?俺ん家に来てくれたご先祖、すでにウチカビで4億円くらい貰ってるからな。逆に何してんの向こうで。
ご先祖は本気で帰ってくる(らしい)
沖縄では魂が本当に帰ってくる』と信じられてるから準備ガチ勢な家庭がめちゃくちゃ多い。仏壇には果物、重箱、お菓子、泡盛、お線香の山盛り。あと、部屋の掃除も完璧にしておく。
つまりあれだ。ご先祖様が帰省するって設定だから、部屋は片付けて、食事は豪華にして、態度もちゃんとしとけっていう親に彼氏紹介する日みたいな緊張感あるんだな。
ちなみに、昔はお墓でも宴会やってたらしい。今はそこまでじゃないけど『先祖はちゃんと帰ってくる存在として扱う』って姿勢は、全国屈指のガチさ。本土の人間が適当に迎え火焚いて終わらせてるうちに、沖縄県民は『魂と心の会話』してんの、ずるくね?
[お迎えの日]ウンケー
意味とタイミング
ウンケーって聞くと『運慶』かと思うけど、そっちじゃないからな。鎌倉彫刻じゃない。こっちはご先祖様をお迎えする日です。
沖縄のお盆は、旧暦の7月13日〜15日。その初日がこのウンケー(御迎え)。
意味はそのまんま「ご先祖様〜今年もお疲れ様です〜どうぞあの世から現世へお帰りください」というあったかいウェルカム魂カムバック儀式。
- ご先祖様「おう!今年も来たぞ!」
- 現世の家族「うわぁ…またこの人、あの世で休まず働いてたんや」
- 神様「今年も仕送り(ウチカビ)頼むぞ。あの世の家賃上がってんだからな」
ご先祖様、マジで帰ってくる想定で迎える。だから仏壇も玄関もピッカピカ。部屋掃除して、飾りつけして、線香セットして、泡盛もお菓子も果物も、テーブルの上に山盛りよ。
そこらの恋人より、よっぽど手厚く迎えられてるのが沖縄のご先祖様たち。「え?俺そんな大事にされてたの?帰省して良かった…」って泣いてるかもしれないぞ。
何をするの?
- 仏壇を掃除
- 線香を焚く(ヒラウコー)
- ご先祖様用の『ごちそう』を用意
- 玄関を綺麗に整える
- 「ウンケーしてきたよ~」って親戚にも言いに行く
- 一部地域ではお墓にも挨拶に行く
線香(ヒラウコー)は長くてデカい奴を数本立てる。香りは『THE 沖縄の家の香り』って感じ。煙を見ながら「あっご先祖様もう来たかも…」って妄想する時間がまた尊い。
こっちは「あっUberご先祖届いたな」くらいの感覚だけど、沖縄県民は『魂が帰ってくる空気』を全力で受け入れてる。
沖縄らしいお迎えの方法
ここが他県との違い。爆竹ドーン、線香ドバドバ、料理ドカ盛り、ご先祖様全力歓迎スタイルが沖縄流。
- ご先祖様「今年の歓迎、なんか例年より豪華じゃない?」
- 現世の人「インフレです。ラフテーも高いんです。感謝してください」
ちなみに爆竹はあの世の門を開く音らしいけど、普通に通報されそうなレベルでうるさいからな。
また、地域によっては、玄関の前に『ススキ』と『米』と『お塩』を置く所もある。それが魂が迷わず帰ってくる目印になるんだとか。GPSの代わりにススキってアナログの極みすぎる。
- ご先祖様「えっと…ススキあったあった。よし、ここが我が家だな」
- 神様「お前去年は隣の家に入ってただろもっと真面目に探せ」
という訳で、ウンケーとは『魂を迎える大イベント』にして『家族が一番真面目になる日』でもある。
本土出身の俺としては、迎え火ちょろっと焚いて終わりとか言ってるのが申し訳なくなるレベル。沖縄、ガチすぎ。魂リスペクトの濃度が違う。
[中日]ナカヌヒー
静かに過ごす日?それとも宴?
ナカヌヒーって何する日っつったら、簡単に言うと『ご先祖様うちでまったりしてて下さいDAY』だな。
沖縄のお盆3日間の中で、ナカヌヒーはちょうど真ん中。だからって「ただの中継ぎか?」って思ったら大間違い。
この日がいちばん、ご先祖様と現世の家族がリラックスして交流する日…って言いながら、家の中は割とてんやわんや。親戚は増えるし、お供えの準備は増えるし、子どもは走り回るし、じいちゃんは泡盛で寝てる。
地域や家庭によっては『静かに過ごす日』とも言われてるが、実際は『親戚で集まってワイワイする日』が多め。この日を『宴』と捉えて、ご先祖様を囲んで『ちょっと良いご飯を出す日』としてる家も多い。
『お供え』と『ごちそう』と『あの世のWi-Fi事情』
ナカヌヒーに限らず、お盆3日間はお供えが命。でもこの日は特に豪華にする家庭も多い。
- 重箱(おかず9種類入り)
- フルーツ(バナナ率高め)
- 泡盛(絶対いる)
- 白ごはんorじゅーしー
- サーターアンダギー(おやつポジ)
- ウチカビ(あの世の紙幣)
これが典型的な供え物リスト。
- ご先祖様「今年の重箱、ポテサラ入ってないやん」
- 現世の母「去年、ポテサラは米に合わんって言ってたのアンタでしょ」
- なをと「何あの世でもクレーム入れてんだよコンビニの客かよ」
ちなみにこの『ウチカビ(紙銭)』ってのがクセ者で、燃やす事であの世の通貨として届く設定。紙燃やして送金て、お前ら昭和のインターネットかよ。
沖縄では『魂』は実在するとされ『ご先祖様は今この空間にちゃんといてこっちの生活を見てる』って考える。だからこそ、重箱の詰め方、線香の本数、料理の並べ方まで本気すぎ。ご先祖様への『おもてなしスキル』が、沖縄県民には染みついてる。
ご先祖様、どんだけVIP待遇されてんだよ俺の誕生日より豪華じゃねぇか。
という訳で、ナカヌヒーは「お迎えしてすぐ追い返すのもアレだから一緒にご飯でもどう?」な日。一部の家庭では、仏壇の前で本気の会話をするし、他の家では子どもがご先祖様ごっこでエイサー踊ったりしてる。ご先祖様も、そんな緩い雰囲気にちょっとホッとしてると思う。「あ〜やっぱ俺ん家良いなぁ」って帰ってくるんだろうな。
[お見送りの日]ウークイ
ご先祖を見送る儀式
ウークイってのは『送る』が語源だ。つまり、ご先祖様をあの世に送り返す日だな。本土のお盆だと『迎え火→送り火』とか言って終わるけど、沖縄は送り火じゃ終わらん。祭りのラストスパートかってくらい、最後に全力でぶち上げる。沖縄のご先祖様はお迎えされたら3日間も滞在するので「さすがに最終日には帰ってもらわなきゃいけない…」って訳で開催されるのがこのウークイ(お送り)。
やることはシンプルだけど重い。
- 仏壇に手を合わせる
- お供え物を整える(または片付ける)
- ウチカビ(あの世マネー)を盛大に燃やす
- 家族全員で真剣に送り出す
ウチカビって毎回思うけど、なんであの世の紙幣は全員金ピカなんだろうな。ご先祖様、燃やされるたびに「今年も課金ありがとよ」って言ってそうだ。
家族そろって手を合わせる意味
この日は、普段バラバラな家族も仏壇の前に集合する。年齢も、仕事も、性格もバラバラでも、ご先祖様に感謝って気持ちだけで繋がる数分間。だからこそ、沖縄の家族って濃いんだよな。ご先祖様という『共通の思い出』が、時間を越えてみんなを一列に並ばせる。
手を合わせるときは、神妙な顔をしてても、心の中で言ってるのは超リアルな願望だったりする。今年こそ家賃滞納しませんようにってな。
エイサーで盛大にお見送り
沖縄のお盆はここからがクライマックス。
太鼓ドーン、掛け声ワッショイ、爆竹ボン。家の外では若者たちが踊り狂う。これが『エイサー』だ。
お盆のラストに出てくるのが若者ってのが、また良いんだよな。ご先祖様を見送るんじゃなく、見送らせてもらうみたいな感覚。伝統のバトンが、太鼓の音に乗って未来に流れてく感じな。エイサーはただのパフォーマンスじゃなくて、ご先祖様をあの世まで送るための祈りでもある。
踊る側も、送られる側も、心が通ってるからこそ、沖縄のお盆は、ちょっと切なくて、ものすごく温かい。ウークイの夜、太鼓の音が遠くに消えていく感じ。あれがご先祖様の帰る足音だと思うとさ、なんかもう「人間って良いな」って思えてくるんだよな…(涙)
とまぁ、こんな感じで沖縄のお盆は3日かけて、本気で迎えて、本気で送る。どれだけ文明が進んでも、AIが進化しても『魂』を信じて大切にする文化が残るのが、沖縄なんだよ。
沖縄県民にとってお盆とは?
信仰でもあるし、イベントでもある
地元のお盆?盆踊りの輪の中に放り込まれて、半笑いの近所のオバちゃんに「踊らなきゃダメよ~♪」って言われて、死にたくなった記憶しかねぇよ。一方、沖縄は爆竹バンバン、太鼓ドンドン、エイサーぐるぐる、親戚どっちゃり集まって、酒と肉と涙の三重奏。おいなんでこんな格差が生まれてんだ。誰だよルール作ったの。
沖縄のお盆は『信仰』と『娯楽』が全力で手を組んでくる。お盆の三日間(ウンケー/ナカヌヒー/ウークイ)ってのは、宗教的意味合いも濃いけど、それと同時に『一大イベント』でもある。
こっちはただの『墓参り』なのに、あっちは『ご先祖様帰還フェス』かよ。なんだその演出ハリウッドか。
仏壇には料理がずらり。親戚がずらり。子どもたちは走り回る。道では爆竹と太鼓。空気は線香の香り。それが全部『ご先祖様を歓迎して送り出すためのもの』ってのが沖縄の凄いところ。遊びと儀式がちゃんと並列にある。
- ご先祖様「信仰のくせに、料理が豪華すぎんだろ…」
- 現世の孫「そっちの世界にもUber Eatsとかあればいいのにねー」
- なをと「それ俺が真っ先に使うわ」
なぜここまで大切にされているのか?
理由はひとつ。沖縄の人々にとって、ご先祖様は『本当に生きてる存在』だから。うちの仏壇にはお爺が住んでるくらいのノリで、日常に魂が息してるんだよな。そりゃ、毎年ちゃんと迎えて、送り出したくなる訳だ。
沖縄は、台風も多いし、資源も少ないし、歴史的に苦労も多かった。だからこそ『人と人のつながり』や『家族の力』が何よりも大事。先祖と繋がってるって感覚がスマホの家族グループLINEよりしっかり生きてる。これが沖縄の強さだな。
そして何より『今の自分たちがいるのは、ご先祖様のおかげ』って意識が、ちゃんと『文化』として根づいてる。家族であり、歴史であり、信仰であり、フェスであり、教育であり、そして何より『生き方の指針』みたいなもの。
地元の盆踊りで感じた疎外感、沖縄のお盆でちょっと癒された気がしたぜ。だってこっちのお盆、ちゃんと人が生きてるんだもん。
最後に
ご先祖様って、ホラー映画の中じゃ呪いの元凶扱いされがちだけど、沖縄じゃ真逆だからね。生きてる家族より優遇されてる説あるくらい神待遇。もはや故人VIPラウンジ。
3日間、ご先祖様のために家を整えて、料理作って、線香焚いて、太鼓鳴らして、爆竹鳴らして、泣いて笑って、踊って送る。ここまで丁寧に人を迎えて送り出す文化、世界中探してもそうそうないと思うぜ。これが沖縄の『強さ』であり『優しさ』であり『人間力』なんだろうなって思う訳よ。
で、これだけやっても、沖縄の人たちは口をそろえてこう言う「なんくるないさ〜」
「なんとかなる」って言葉、適当に聞こえるかもしれねぇけど、ご先祖様も一緒に「なんとかしてくれる」っていう信頼と歴史の積み重ねの上に成り立ってんの。そう考えると「なんくるないさ〜」って言葉、とんでもなく重くて、あったかい。
ご先祖様を大切にするってのは『自分たちのルーツを誇りに思う』って事でもある。自分がどこから来て、誰に繋がってて、どんな想いを背負って生きてるか。
それを年に一度、お盆って名前のフェスで、家族総出で確認してるって思うと、そりゃ…羨ましくもなるわな。

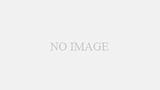

コメント