うちなータイム。初めて聞いた時、俺は思いました。「あ〜またゆとり教育が生んだ新種の言い訳か」と。でも違った。これはただの遅刻とか、やる気がないとかそんな安っぽい言葉で説明しちゃいけない文化爆弾でした。
予定は未定。開始時間は目安。「今向かってる」はだいたい家出る10秒前。なのに、誰も怒らないし、誰も詰めない。むしろ「遅れても元気ならOK」っていう奇跡の国がそこにある。
移住してからというもの、俺は時計を見ることをやめました。予定を守れなくなったのではない。予定が俺を守らなくなったのだ。
本記事では、この沖縄特有の『ゆるやかなる時間泥棒=うちなータイム』について、その成り立ち、文化的背景、沖縄県民の価値観と合わせて、ガチで深掘りして叩き起こしてみたいと思います。
そして最後には、きっとあなたも言ってしまう事でしょう「まぁいっか」ってな。
うちなータイムとは?
定義と本土との違い
『うちなータイム』とは時間にルーズであることに全力で正当性を持たせた沖縄の時空魔法である。
「13時集合ね〜」と言われても、実際に人が揃うのは14時過ぎ。それに対して「遅いぞ!」と言ったら怒られるのは、なぜか時間を守った側のほう。理不尽?いやこれは文化であり、哲学だ。
本土の常識では『時間=信頼の証』
でも沖縄では『時間=目安』で信頼は笑顔で証明。予定は未定、未来は天気次第。
特に内地の秒単位で動く人種からしたら、この時間の概念のふわふわ感に最初はイライラするかもしれない。でもそれこそが罠だ。時間に縛られてる自分こそ、不自由だということに気づくまでがデフォルト。
つまり、うちなータイムとは「時間なんて人間が作った都合だろ?もっと大事なもん見ろ」っていう沖縄の哲学。
実際にどんな場面で現れるのか
集合時間
「10時集合ね〜」
10時に着いたら自分しかいない。だが誰も謝らない。全員が「まだ来てないだけ」と受け入れる。
イベント開始時間
開始予定:18時
実際に始まる:18時45分
司会「はいさ〜い!ちょっと遅れましたが始めましょうね〜」
バスの発車時間
発車時刻の3分前にバスが行ってしまう。
理由?運転手がもう乗る人いないと思ったから。信じるな時刻表、信じろ勘。
飲み会
一時間遅れてくるやつ、2時間後に現れるやつ、店を間違えるやつ。
でも全員「はいさーい!」って乾杯して終わり。それでいい。
まとめ
うちなータイムとは、遅刻という罪を文化で包み込んだ沖縄最大の免罪符。でも不思議な事に、そんな場所だからこそ、誰もピリピリしないし、人間関係もやたら長続きするし、時計よりも人を見て生きてる。だから俺はもう、時間を守らなくなった。じゃなくて時間に縛られるのをやめたんだ。
起源
沖縄の歴史的背景(島時間と独自性)
まず前提な。うちなータイムは『遅刻』じゃない。それは『生き方そのもの』なんだよ。
沖縄はかつて独立国家『琉球王国』だった。本土とは別文化、別言語、別政体。貿易も盛んで、中国や東南アジアとの交流も長い。つまり『時間は正確に守るもの』という本土的な価値観とは、文明の段階からズレてる。
じゃあその王国の人々、どうやって時間を見てたか?
「太陽がここまで来たら出発する」
「月がこの辺に来たら寝る」
それで何百年も上手くいってた。つまり『時間』ってのは『分単位で縛る鎖』じゃなくて『自然と体感で感じるもの』だった。
しかもだ。この感覚的な時間が、社会的に許容されてきたのが凄い。
船の出港も「風が吹かないからまた今度」
集会も「なんか台風来そうだから中止」
自然に従う=神に従う。遅れるのは天命。誰も責めない。これが琉球の精神文化。で、それがそのまま今に残ってる。それがうちなータイム。
暑さとゆるさの関係性(気候的理由)
気温と文化の関係。ナメたらいかん。夏が暑すぎると「運動したら死ぬ」ってなる。でも沖縄の暑さは『蒸す』より『照る』タイプで、しかも年中これ。
「この気温で、時間通り動けって無理だろ」
「焦ったら倒れるわ。死に急いでどうする」
結果どうなるか?
『急がない』が生存戦略になる。
しかも『夏が長い=時間が長い=そんな急がなくても後でまたできるだろ』という思考が染みつく。さらに台風が来るたびに予定は消し飛ぶ。イベント延期、出勤中止、学校休校。予定=未定が生活の中に組み込まれてる。
これで時間に厳しくなれると思う?無理だよ。身体が拒否する。人間は自然には勝てない。だから自然に合わせて、ゆるく生きるしかない。それが気候的理由。
急がない事が美徳という価値観
本土の価値観=「遅刻はダメ!社会の迷惑!」
沖縄の価値観=「そんなに急いでどこ行くの?」
もうこの時点で正義が違う。沖縄では『せっかち』はむしろ『人にストレスを与える存在』として見られることすらある。
実際にはこんな話がある。
「あの人、いつも時間通りで逆に怖いよね」
「仕事早すぎて、みんなペース崩れるから迷惑」
…え?まじで?うん本気で言ってた。沖縄では『周囲と調和を取る』事が最上の美徳。自分のペースで動く人より、空気読んでみんなに合わせる人の方が評価される。だから『みんな遅れるなら自分も遅れる』は協調性なの。
そして忘れちゃいけない。
「時間を守ることが正義」って誰が決めたの?
「守って得られるものがあるなら、それで良いけど?」
「でも沖縄では、守らない事で守れる空気がある」
つまり、急がない事こそが『沖縄的優しさ』であり、美徳なんだよ。
体験談
出勤時間退勤時間はちゃんと守るけどプライベートは野生に還る
何がクソって、仕事中は秒単位で真面目なのに、プライベートになると時空が溶ける。さっきまで働いてた人類とは思えないほど、野生に還る。
「ランチ11時集合ね!」11:30集合(やる気はある)
「映画13:00からだよ!」13:05に到着(え?)
なぜ急に猿になる。
普通にウソつく
LINEで「今から家出る」は「今起きた」という意味で「もうすぐ着く」は「今家出た」という意味。
Google翻訳でも無理な沖縄語の魔術。LINEを信用する者はバカ。
- 「今から家出るわ〜」
- 「シャワー浴びてくるね〜」
- 「もうすぐ着く!」
- コンビニ
- 寄り道
- 信号3つ無視
- 30分後到着
こっちは時計見ながらソワソワしてるのにあっちはクーラー効かせてアイス食ってるからな。
集合時間通りに着いたのに「早い」と言われた
意味がわからん。俺の時計がバグってんのか?
- 12:00集合予定
- 12:00着のLINE「えっ早っw」
- 12:15になっても誰もいない
- 12:30にLINEで「今出るね〜!」
「遅い」じゃなくて「早い」って言われる国、それが沖縄。時間守る奴がむしろ空気読めない奴になるという、逆転裁判がここで開廷。
むしろ来ない奴もいる
来ないとかじゃない。来るという概念がない。集まるっていうのが『全員来る』じゃない。来たい奴が来たい時間に来る。そして誰も責めない。
「〇〇来てないじゃん」
「うん多分今日は来ないよ〜」
それで終わり。全員ノーダメ。罪の意識ゼロ。
最後に
最初はキレた。時間にルーズな奴らに、LINEの嘘に『今向かってる詐欺』に、何度殺意を抱いたか知れない。
「集合時間は命の約束だろうが!」と叫びたかった。ていうか叫んだ。6回ぐらい。
でも気づいたんだ。ここは沖縄。時間に追われるために生きてる訳じゃない。こっちが『合わせよう』としなきゃいけない世界なんじゃなくて『自分に合った時間』で生きて良いって世界だったんだ。時間を守らないんじゃない『時間に縛られない』んだよ。
時計を見て焦る生活より、太陽の動きと腹時計で生きる方が、多分、人間として正しいんだろうな。という訳で、俺は今日も「今向かってる」と言いながら寝てます。ありがとう沖縄。俺の人生3時間遅れで絶好調です。


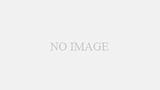
コメント